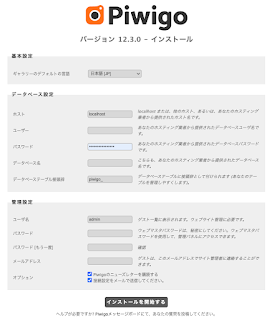小学生低学年(とその親40代初心者)が使う チェロの椅子 を探す!

こないだ、次男坊(小1)がチェロをしたいと言い始めて、チェロ始めました。その前まではバイオリンしてたのですが、挫折?休憩?中でまた戻る!と言っていたのですが、チェロに転向するようです。。 自分も大学生時代に近くの音楽教室が閉鎖する際にチェロかコントラバスがあれば欲しい、と伝えていたところ、チェロが出てきました。(R&B, HipHopが好きだったのでそっち系で使いたかった)その時から所有はしていたのですが、ぜーんぜんピッチが取れず面白くなくてギターばかり弾いていました。(あの頃から先生探せばよかった、ほんとに。)で、最近子供がバイオリン習うようになって、こうやって練習するのか!と気づき、40歳超えてから実家からチェロひっぱり出してきて、弾くようになりました。 前置きはこれくらいで、チェロの椅子です。うちの子は115cmぐらいで1/4スケールのチェロ弾かせてます。先生のうちに行った時に「椅子が高いね」となって、「そうなんですよね、何か用意しないとダメですかね?」という話をしていたら、「お風呂の椅子とかいいみたいですよ」って教えてもらいました。で、調べてみると、確かに子供用のチェロの椅子がない問題はあるようで、みんなこれで代用しています、これで決まり!的な情報があります。 でも、なんか欲しくなくてですね。。だって、いくら良い高さの椅子がないかららってお風呂の椅子に座って弾くのも…って感じするじゃないですか。で、私も調べました。要するに30cmぐいの高さのそれっぽい椅子があれば言い訳です。で、調べてみると、確かにほとんどない。。ピアノ椅子やチェロ椅子は子供をカバーできる高さ調整はできないのが普通のようです。 そんな中、ありました!30cm以下まで下がるピアノ椅子っぽい、いわゆるキーボード椅子?! 足がクロスして支えるやつです。110cm前後のお子さんがチェロ弾く時にはこれで決まりです!! イーサプライ ピアノ椅子 キーボードベンチ X型 幅60cm 高さ調整7段階 26~50cm 低め クッション 厚さ8cm 折りたたみ EEX-CHS03BK 7段階(26・30・34・38・42・46・50cm)も調整できます!私も使っています。もう今までのスツールには戻れないです。疲れないので、長時間弾けるようになりました! 型番アップしておきます。みんなもこれにし...